こんにちは。
パニック障害専門カウンセラーの三木ヒロシです。
聞いたことがある人もいるかと思いますが、「死生観」という言葉があります。
「死生観」とは、生きること、死ぬことに対しての考えかたであり、「死生観」の考えかたは人それぞれ違います。
死ぬことや生きることに意味を見出そうとする人や、死についての考えはあるものの生きるの考えが無い人、または反対に死についての考えが無い人など、様々です。
そして、実はこの「死生観」が深くパニック障害と関連しており、「死生観」の考えかたでパニック障害に陥る、陥らないが分かれるとも言えるでしょう。
今回は、パニック障害と「死生観」の関連についてお話をしていきましょう。
目次
「死生観」とパニック障害の関連とは?
先ほど「死生観」とパニック障害は関連があると述べました。
ではいったい、どのようなことが関連あるのでしょうか?
まず、パニック障害に陥ってしまう人はある意味「死」というものに対して自分なりのネガティブな解釈があることがほとんどです。
とは言っても、人間である以上「死」についてネガティブな解釈をしてしまうのは当然であり、「死」についてよほどの宗教家でもない限りポジティブな解釈はできないものです。
ですが、パニック障害に陥ってしまう人の「死」への解釈と、陥らない人の「死」への解釈には大きな違いがあります。
それは、パニック障害に陥ってしまう人は「死」に対して心の奥底に強烈な恐怖や不安があり、できるだけ「死」という考えは思い浮かべたくないと考える、思うものです。
一方、パニック障害に陥らない人は「死」に対する恐怖や不安が無いというわけではありません。
もちろん「死」に対する恐怖や不安はありますが、強烈というものではなく、どちらかというと「死」は必ず来るべきもの、という認識が無意識下にあります。
一度や二度起きたパニック発作が継続的に続いてしまうパニック障害に発展してしまうのは、この「死」への怯え、怖さ、不安が強く渦巻くからであり、その渦巻いた感情がパニック障害を深くこびりつかせるとも言えます。
逆に言うと、「死」についての怯え、怖さ、不安といった感情に繋がる「死生観」を違う方向に向けることができれば、おのずとパニック障害は和らいでいくと言えるでしょう。
「死」に対しての考えを変えていくのはとても難しいことではありますが、ひとつの方法論としては大切なことでもあります。
「死生観」を変えていくにはどうすればいいのか?
パニック障害に陥る心の奥底にある、どちらかというとネガティブな印象の「死生観」。
では、実際に「死生観」を変えていくことはできるのでしょうか?
ここからは「死生観」を変えていくため、取り組むと良い方法について述べていきましょう。
「死」への認識を広げてみる
「死」というとどちらかといえばタブーな印象があり、普段の生活では自分から進んでなかなか触れる機会は作らないものですよね。
ですが、あえて「死」についての本を読む、「死」とはないか調べてみる、仏教を学んでみるなど「死」についての認識を広げてみると良いでしょう。
仏教はどちらかというとこの世界を生きていくための学びですが、生きる視点から「死」を読み解いていくと、色々と見えるものがあるかもしれません。
色々な角度から「死」への認識を広げていくことで、自分の中で凝り固まっていた「死生観」が変化を及ぼす可能性があります。
「死」について語り合ってみる
普段の生活のなかで「死」について、なかなか話したり語り合う機会はないのではないでしょうか。
あえて口に出して話してみる、ご家族やパートナー、友人などと語り合ってみると、人それぞれの解釈に触れることができ、良い意味で自分の「死生観」に変化が起こるかもしれません。
「死」についてネガティブな印象しかない人もいますので話す、語り合うのは難しい部分もありますが、機会があればそのような場を持ってみるのも良いかもしれません。
自分のなかの「死」について書き出してみる
人間は頭のなかにあること、残っていることは段々と膨らみ拡大解釈になってしまうことも少なくありません。
本来は小さく頭のなかにあったことが、気がついたらあれもこれもと付け加えられてしまい、まったく違う大きなものへと変わってしまうことがあります。
これは良くも悪くも人間はイメージできる生き物ですので、頭のなかにあるイメージが書き換えられてしまうことから起こる現象なんですね。
一旦頭のなかにあることを紙やノートなどに書き出してみる、アウトプットしてみることで視覚化でき、整理されることは多々あります。
また、あえて書き出してみることで拡大解釈されている不自然さにも気がつくことは多く、本来の姿を把握することができます。
「死」というものを書き出してみることで、改めて気がつくこともあるでしょう。
お寺の住職などに「死生観」についての考えを聞いてみる
お寺の住職などはお役目柄、「死生観」について様々な見解を持っていることが多く、機会があれば聞いてみるのも良いでしょう。
「死生観」は説法の題材になることもあり、ある意味一般人にはない「死生観」を聞けるかもしれません。
また、インターネットで検索すると大僧正、大阿闍梨などの説法が掲載されていたり、動画に出演していることもあるので、そのようなものを見つけてみるのも良いでしょう。
説法はいろいろな観点からのものが多く、動画を見ているだけでも色々なものに触れることができます。
終わりに
普段の生活では意識しない限りなかなか触れることのない「死生観」。
ですが、パニック障害に強く紐づいていることは多く、ネガティブな「死生観」があるからこそパニック発作への恐怖、不安もひと際強いとも言えます。
パニック障害の完治・改善のためあえて「死生観」を深堀りしてみる、「死」についての解釈を並べてみることで見えることもあるでしょう。
「死」というキーワードはある意味センシティブなものでもありますので、無理のない範囲で時には聞いてみる、語り合ってみると良い意味で視点が変わるかもしれません。
p.s パニック障害改善への近道を知りたい人はいませんか?
パニック障害の完治・改善が進んでいくのは2通りあります。その2通りとは、
・パニック障害の完治・改善まで遠回りしていくか
・パニック障害の完治・改善まで近道をしていくか
というものです。
私も過去に数回パニック発作の経験がありますが、その後はパニック発作が起こることはなくピタリと終わりました。
それはなぜか?
パニック発作が起きたとき、そのときはすでにパニック発作を解消させていくスキル、パニック障害に陥らない知識、どのようなことをおこなっていけばパニック発作を解消できるのか?を知っていたからです。
そして、そのような知識はもちろんですが、パニック発作に至るまで数回のカウンセリングを受けていたから最悪の事態にならなかったとも言えるでしょう。
個人の力では限界があることでも、専門家が寄り添い一緒に歩んでいくことで解決・解消できることは多々あります。
パニック障害の完治・改善まで遠回りせず、望むゴールにたどり着く方法として最適なのがパニック障害の専門家によりカウンセリングと言えるでしょう。
パニック障害専門カウンセラー三木ヒロシのカウンセリングは下記のリンクからお申込みが可能です。
リアル対面でのカウンセリングからオンライン、電話カウンセリング、メール相談など状況や状態に合わせてお選びいただけます。
カウンセリングの詳細につきましては下記リンクからご覧ください。
↓↓↓↓↓↓
本日も最後までお読みいただきましてありがとうございました。
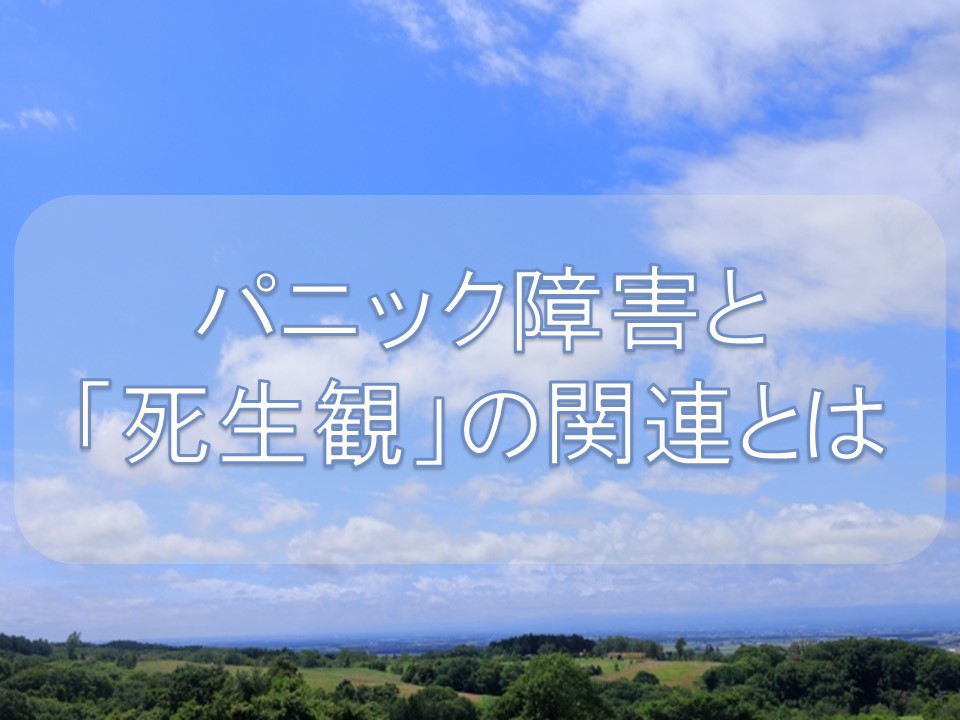




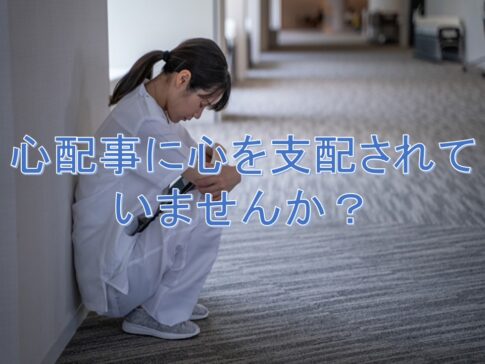
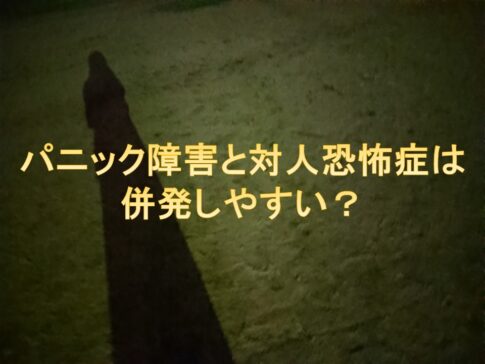


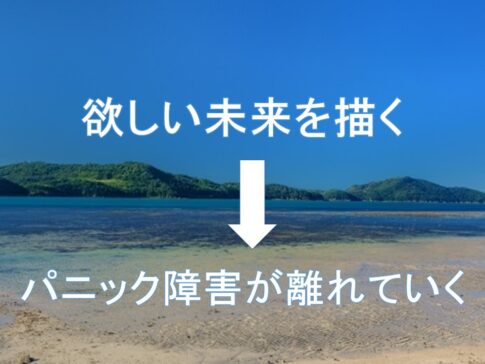
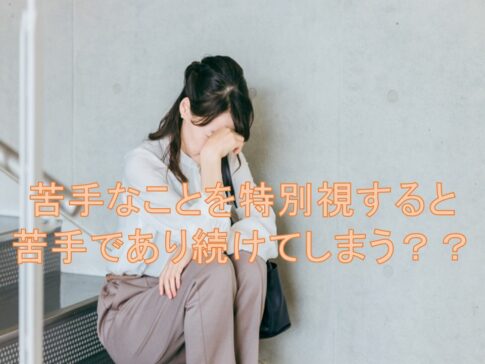

コメントを残す